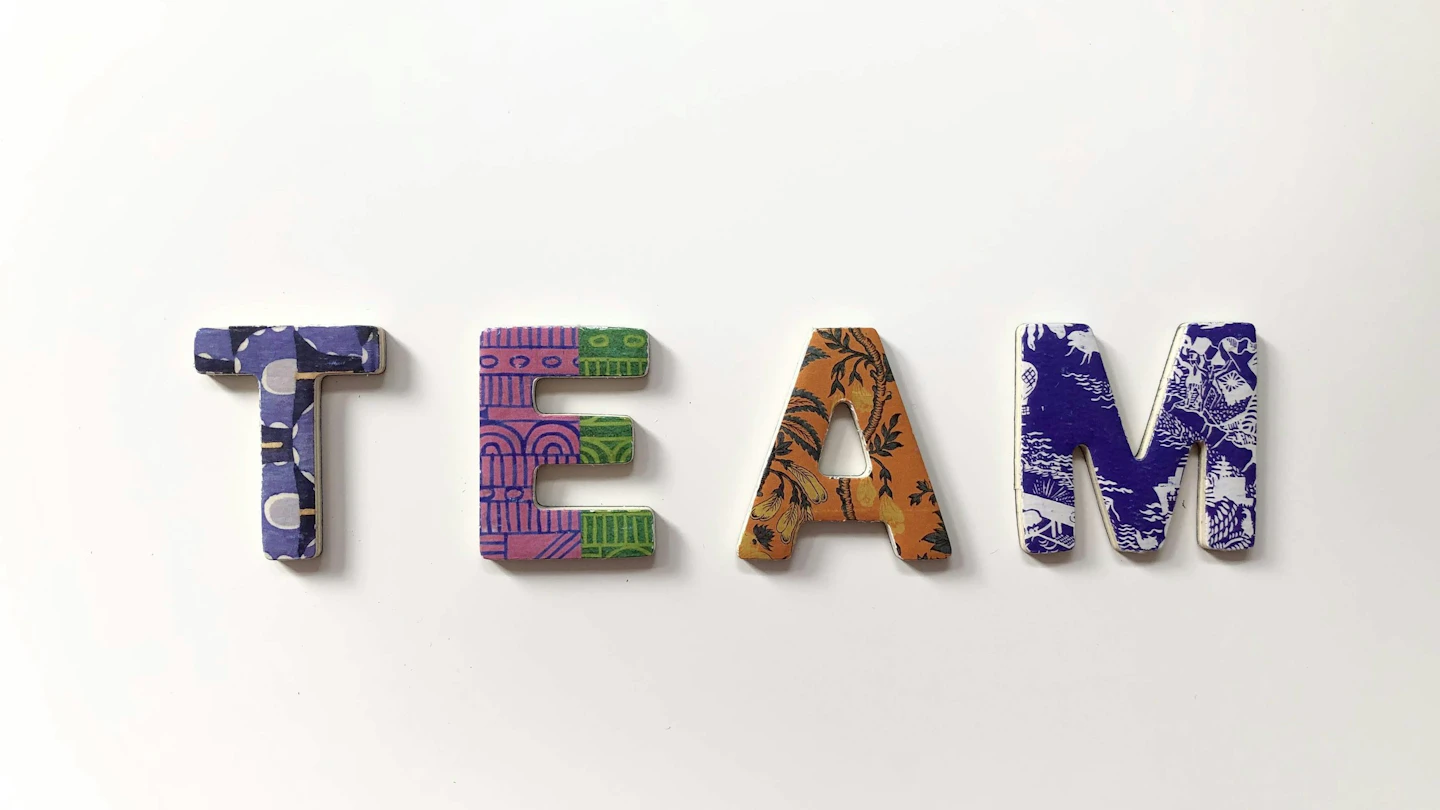エンゲージメント向上にはミドルマネジメントの関与が重要
Authored by 井手 寛暁, 組織開発ダイレクター, パーソルコンサルティング 中国
エンゲージメントの本質=「チームの一員」という感覚
前回のコラムでは、エンゲージメントの本質は、「組織と社員の双方向の要求が釣り合う状態」であることをお伝えしました。組織は社員に役割責任と期待成果を求め、社員は組織にキャリア形成の機会や良好な環境等を求めます。この相互要求の均衡点こそが、社員の主体性を引き出すエンゲージメントの高い状態を生み出すのです。ADPリサーチ・インスティテュートのグローバル調査で示唆されたこととして、この均衡は、「社員がチームの一員であると感じている」という要素から生まれるということです。
「チームの一員である」という感覚は、次の2つの要素が組み合わさって生まれます:
・自己効力感:自身の力がチームの成果に貢献しているという実感
・認知・承認:その貢献がチームメンバーから認識されているという確信
そもそも、チームで仕事を行う本質は、単なる集団作業ではなく、「目標達成のために生産性の高い方法をとる」ことにあります。そのためには、メンバーが互いの能力を理解し、メンバー各々が得意分野で勝負できる役割(アサインメント)を与えられることが前提となります。その結果として、自己効力感、認知・承認が生まれ、エンゲージメントが発現し、異なる能力を組み合わせて新たな価値を創出される。これがチームとして目指すべき状態であると考えます。
役割の明確化の重要さと難しさ
上述したように、チームとして力を発揮する上で、「個々の役割(アサインメント)の明確さ」は重要な要素です。特にアジアでは、この点が業績を左右する側面があるのと考えます。
- 飲食店の海外展開事例:
日本式の「多能工」を海外では期待しにくいのが実態です。アルバイト社員に対して、日本におけるアルバイト社員の担当分野を細切れにし、「細かいタスク」を一人ひとりの役割として付与することで、安定した店舗運営を実現するケースをお見受けします。こうすることで役割の曖昧さ(自身の判断でタスクを切り替える等)を排除し、明確なアサインメントを行っていると言えます。
- 中国サッカー(富士通総研 柯隆氏):
個人競技(卓球等)が強い中国ですが、チームスポーツ(サッカー等)になると決して強いとは言えません。チームスポーツでは、一度フィールドに出ると、自身の判断で自身の役割を柔軟に変化させ続ける必要があります。監督が事細かに指示を出したり、自身の本来の役割に籠っていると、チームとしての柔軟な対応はできません。中国人は明確な役割分担の下で、個人として明確に評価される状況を好むがゆえに、チームスポーツが強くないと言われています。組織として業績を創出するためには、一人一人の役割(アサインメント)をクリアに切り分けた方がうまくいくことを示唆しています。この傾向は中国のみならず、ASEANでも同様ではないかと思います。
とはいえ、ビジネスの現場では、一人一人の役割をクリアカットに切り分けるのは困難です。社員が自ら考え動く主体性が不可欠であり、社員がエンゲージメント高く主体的に動いてくれることで、優秀な人材は自らの真価を発揮できる側面があるのです。
キーパーソンはミドルマネジメント
この難題を解く鍵こそ、「現場のミドルマネジメント(現場マネジャー・スーパーバイザー)」です。彼らはエンゲージメント形成の「起点」であり「到達点」を担う存在と言えます。
エンゲージメントが発生している「組織と社員の要求の均衡」の状態は、現場で自然に生まれるものではありません。両者の期待を「意図的・継続的にすり合わせる媒介機能」が不可欠です。ミドルマネジメントはこの機能の担い手として、次の機能を果たす必要があります。
・社員の期待を汲み取る:各メンバーのキャリア観や働きがいの源泉を理解する
・組織の期待を伝達する:チーム目標と個人の役割を明確に示す
・認知・承認を示す:貢献を具体的に評価しフィードバックする
このプロセスを怠ると、現場での仕事要求と自身の期待とのギャップを社員は自己解釈で埋めようとします。結果的に社員の誤認識や不満が生まれ、それを見聞きした経営層からは「社員は金でしか動かない」といったコメントが飛び出すという、組織としては不幸な状態になってしまうことさえあります。上記の機能のうち、絶対的な起点は「社員の期待を汲み取る」ということです。社員の期待を認識した上で、組織の期待を伝達し、認知・承認を示すことで、組織と社員の要求を常に均衡させるコミュケーションが求められるのです。
会社が導入すべき「期待すり合わせ」の仕組み
重要なのは、ミドルマネジメントのすり合わせ機能を「持続可能」にするために、「仕組み」を通じて定着させることです。ミドルマネジメントの能力・努力頼みにせず、会社としてすり合わせのコミュニケーションを促進する仕掛けを導入することを推奨します。
具体的な例として、リーバイスの “Celebrating Failure(失敗を祝う)”施策は参考になります:
「部下が失敗を報告した際、上司はまず報告への感謝を示す」
この単純なルールだけですが、効果は大きいと言います。 部下が早期に問題を報告しやすくなる、上司と部下が協力して対策を考えられる、隠ぺい文化の防止と心理的安全性の向上等、会社の望む文化を醸成する機能を果たしています。
こうした仕組みは、経営と現場の考え・期待のすり合わせを促進するだけでなく、「失敗から学ぶ」「正直な報告を価値とする」 といった組織文化そのものを形作ります。結果として、社員の主体性を尊重しつつ、エンゲージメントを高める好循環が生まれるのです。